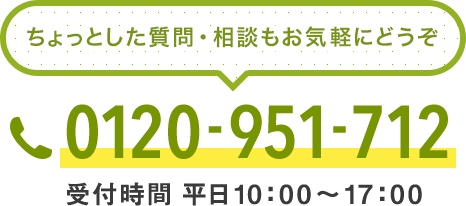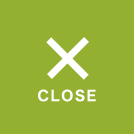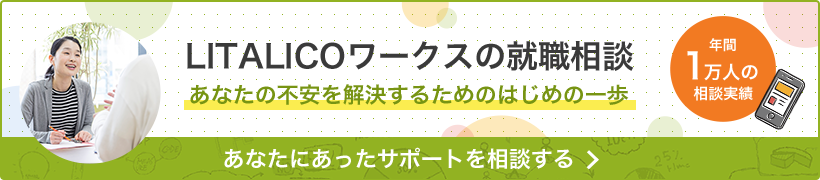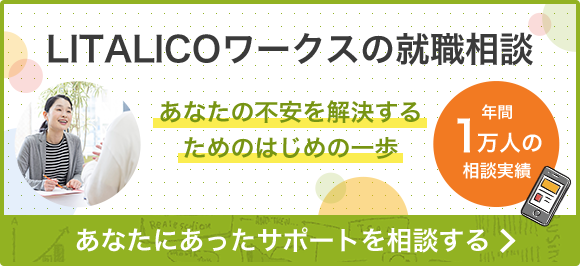不安障害(不安症)とは、分かりやすくいうと強い不安感や恐怖心によって、生活に支障がでている状態をいいます。不安障害(不安症)にはいくつかの種類に分かれており、人によって症状の表れ方はさまざまです。例えば「人前でスピーチをしようとすると、身体が震えて話せなくなる」といった症状が挙げられます。不安障害(不安症)は、決して本人の努力不足や甘え、性格によって引き起こされるものではありません。
今回は不安障害(不安症)の症状や診断基準、治療方法、対処法や対策について分かりやすく解説します。
(※)現在、診断名は「不安症」となっています。(DSM-5-TR『DSM-5-TR 精神疾患の診断・統計マニュアル』)旧診断名の「不安障害」で診断された方も多いため、本記事では「不安障害(不安症)」の名称を使用します。