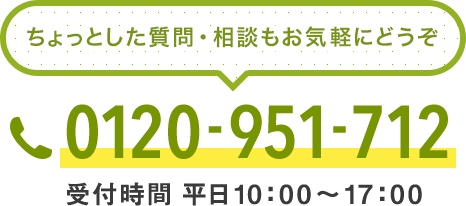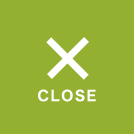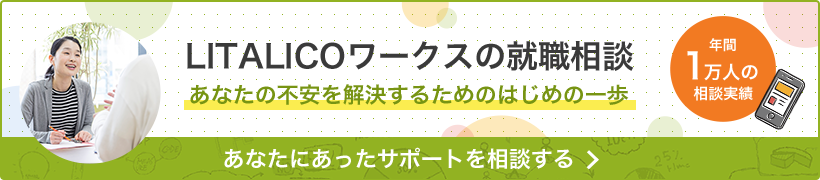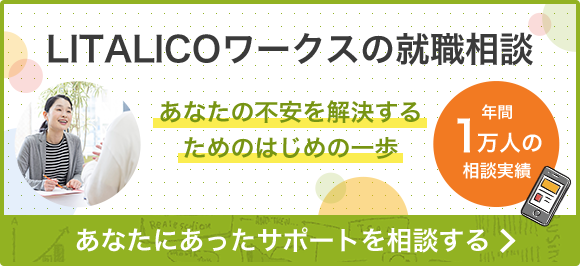職業訓練について「職業訓練は誰でも受けられる?」「毎月給付金をもらいながら無料で資格取得ができる?」「受講できるコースはどのようなものがある?」など、疑問を感じている方もいるかもしれません。
職業訓練とは、働くうえで必要なスキルや知識を習得できる公的な制度で、正式名称は「ハロートレーニング」といいます。
職業訓練はスキルや知識を習得できるだけではなく、一定の条件を満たす方は受講手当として給付金を受け取れるという点も大きな特徴です。また、コースの種類は事務系やIT系、資格取得を目的としたものなど幅広く興味のある分野から選べます。
この記事では、職業訓練の概要や種類、給付金の条件、受講の流れなどを解説します。