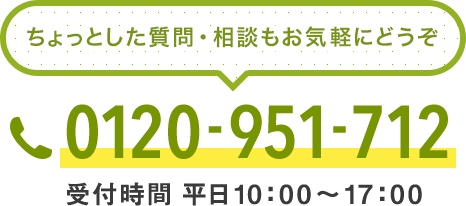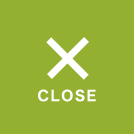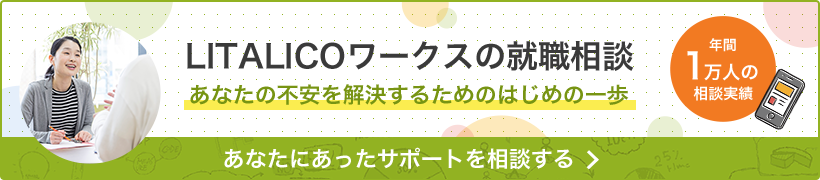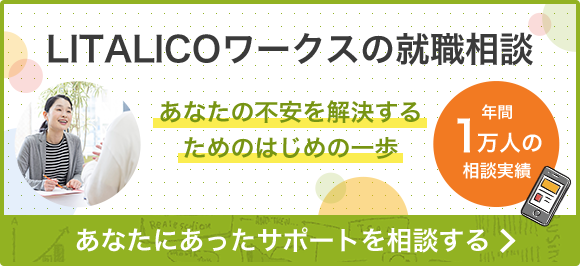コミュニケーションや仕事の進め方などにおいて、どうしてもうまくいかず困ってしまうことはありませんか?それはもしかしたら「発達障害」が原因かもしれません。
現在、大人になってから初めて「発達障害」と診断される方が増えています。
発達障害とは、主に3つに分けられます。
- ASD(自閉スペクトラム症)※1
- LD・SLD(限局性学習症)※2
- ADHD(注意欠如多動症)※3
この記事では、発達障害のうちのひとつである「ASD(自閉スペクトラム症)」はどういった特徴・特性があるのかについて解説します。また大人の当事者の方が直面しがちな職場などでの困りごとの対策についても、詳しく見ていきます。
※1以前は「自閉障害」という診断名が用いられていましたが、アメリカ精神医学会発刊の『DSM-5』(『精神疾患の診断・統計マニュアル』第5版)において自閉的特徴を持つ疾患が統合され、2022年(日本語版は2023年)発刊の『DSM-5-TR』では「自閉スペクトラム症」という診断名になりました。この記事では以下、ASD(自閉スペクトラム症)と記載しています。
※2学習障害は現在、「SLD(限局性学習症)」という診断名となっていますが、最新版DSM-5-TR以前の診断名である「LD(学習障害)」といわれることが多くあるため、ここでは「LD・SLD(限局性学習症)」と表記します。